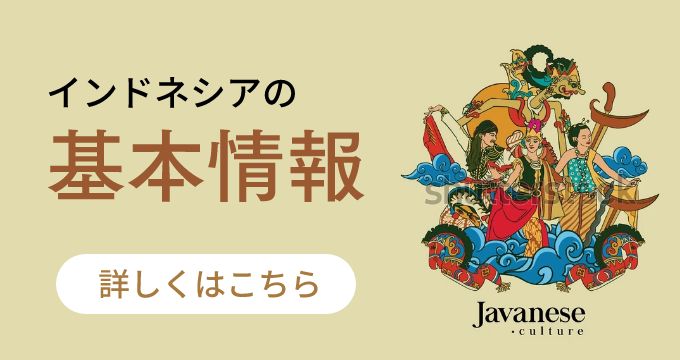住む
インドネシアの交通事情

「世界で最も渋滞問題が深刻」と言われているインドネシアの首都ジャカルタ。
人口約3,120万人と東京首都圏に続いて世界第2位の大都市にもかかわらず、公共交通機関は未発達です。
「インドネシアの道路状況はどうなっているの?」
「移動するときは何を利用すればよい?」
「もし何かトラブルが起きたらどうしたらいいの?」
このように悩む方も多いのではないでしょうか。
バイクの利用者が多く、車の間を縫うように走っているため、横断歩道を渡ったり道路の脇を歩いたりすることは非常に危険です。
そこで今回は、インドネシアの交通事情について詳しく解説していきます。
Contents
インドネシアの道路事情

インドネシアの道路は常に混雑し、信号の順守は不十分でスピード違反や割り込み運転は日常茶飯事。歩行者優先の考え方もありません。そのため、多くのドライバーは歩行者が避けると思っています。
自動車だけではなくバイクも容赦なく突っ込んでくるので、歩行時は十分に注意しましょう。
特に交通渋滞が発生しやすいのは、出勤時・昼食時・退社時。
信号機があまりなく一方通行が多いため、目的地まで予想以上に時間がかかります。
インドネシア国内を移動する際は、時間に余裕を持って行動しましょう。
一時的な渋滞対策
「3 in 1」(スリー・イン・ワン)は、ジャカルタの渋滞を緩和するためにつくられた制度になります。
朝7:00-10:00と夕方16:30-19:00の間は、乗車人数が3人未満の車両(タクシー以外)は通行できないルールとなっています。
そのため、子供を寝かしつけて車に乗せていたり、3人目の1人になるために道端で手を上げて、車に乗り合うこともあるそうです。道を通っていると気づくこともあるかもしれませんね。
ちなみに、3人未満の状況で警察に見つかった場合、罰金が課せられるのでご注意ください。
ジャカルタ市内の交通手段

ここでは、ジャカルタ市内の交通手段について紹介します。
主な移動手段は、以下の5つ。
- ドライバー付き自動車
- 電車
- バス
- タクシー
- バイクタクシー
安全に移動するための方法を把握しておきましょう。
ドライバー付き自動車
ジャカルタで仕事をしている日本人駐在員の多くは「専用ドライバー付き自動車」を利用しています。
下記の理由から、ほとんどの企業が自分で運転することを禁止にしています。
- 頻繁に車線変更するドライバーが多い
- バイクが急に割り込んでくる
- 歩行者を見ても停止しない
- インドネシアは国際免許の条約に加盟していない
タクシーよりも高くなってしまいますが、安全かつ安心して利用できます。
電車

ジャカルタ市内を走っている鉄道は、以下の3つ。
- MRTジャカルタ:都市高速鉄道でジャカルタの中心を南北に走る約16kmの路線
- LRTジャカルタ:州営の高架式LRTで北ジャカルタのクラパガディン地区を約6km結ぶ路線
- LRTジャボベック:国鉄KAIが運営する高架式LRTでドゥクアタスからブカシティムールとデポックに分岐する約33kmの路線
MRTは2019年3月に開業し、約2年で累計乗客数が3,300万人に達しました。
電車の開業は移動しやすさの向上だけではなく、大気汚染や交通渋滞の改善にも役立っています。
今後ますます開発が進み、利用者も増えていくでしょう。
バス

ジャカルタ市民が最も利用しているのが「トランスジャカルタ」と呼ばれているバス。
トランスジャカルタは、道路中央に設置された専用レーンを走行しています。
海外から訪れた観光客でもわかりやすい運転経路になっており、今では1日に70万人以上の人が利用しています。料金は約28円と格安で、改札を出ない限りどこまでも乗車可能。
うまく使いこなせば、ジャカルタ内をかなりおトクに移動できます。
タクシー
日本人がインドネシアを訪れる際は、専用自動車もしくはタクシーを使うのがよいでしょう。
在インドネシア日本国大使館からも、タクシー利用時に関して以下のように呼びかけられています。
- ホテルやレストランから呼んでもらったものに乗る
(Gold Bird/Silver Bird と呼ばれる、黒塗りの高級車と呼ばれるもの) - ホテルで客待ちしているものを使う
- 深夜に流しのタクシーを拾うのは避ける
- 運転手証を確認し、別人であれば直ちに降車する
またバイクで後方から追いかけてきて車内のかばんを盗んだり、凶器を出してお金を要求する手口の犯罪が多発しています。
被害を抑えるためにも、下記の2点はおこなっておきましょう。
- 乗車したタクシーの車両番号・運転手名・タクシー会社名をメモする
- 知人に携帯電話で伝えておく
バイクタクシー
急いでいるときに利用する人が多い、バイクタクシー。
渋滞のなかでも車の間を通り抜けられるという観点から機動面では魅力的ですが、事故も多いので安全面ではおすすめできません。
利用はできるだけ避け、自分の身は自分で守りましょう。
ほかのエリアの交通手段

ほかのエリアでは都市によって交通手段は異なりますが、よく使われているのはタクシーです。
バリ島での移動手段は「ブルーバードタクシー」が比較的安心だと言われています。
名前の通り「青い鳥」のマークが目印ですが、最近ではそっくりな偽物のタクシーもあるようなので注意してください。
本物のブルーバードタクシーと呼ばれるものは女性でも乗車しても安心と言われています。また、日本円にして約80円と初乗りも安く移動するのにおすすめです。
最近では、配車アプリ「Grab」も導入され、少しずつ移動のインフラにも変化が起きています。
また、昔ながらのレンタサイクルを利用する際は、盗難や修繕代の請求に気を付けましょう。
ブレーキが効かなかったりギアがすぐに取れたりして修理代を求められます。
自転車のカゴに入っているカバンを狙ったひったくりも多発しているので、自身の持ち物には最新の注意を払うことが大切です。
バジャイ
2〜3人乗りの三輪自動車「バジャイ」。
バイクタクシーは荷物を載せられず、雨の日には濡れてしまいますが、バジャイはビニールクロスで覆われているため、その点が補われています。
またジャカルタ市内の狭い道も通れることから、現地の人にも人気な乗り物です。
あまり早く走れないため、遠距離での移動や時間がないときの利用には向いていません。
値段はタクシーと同じくらいですが、交渉制のため観光客はぼったくりにあう可能性が高いです。
バジャイに乗る際には、料金交渉をきちんとおこないましょう。
もしも交通事故にあったら?
少し古い資料になりますが、在インドネシア日本国大使館 在ジャカルタ日本国総領事館 ジャカルタ・ジャパン・クラブより「インドネシアで安全に暮らすために」という資料が配布されています。
海外で交通事故等に巻き込まれることは稀ですが、知っておくと良いこともあります。
1、車を利用するなら、信頼できる運転手に依頼し運転をお願いする
基本的に交通量の多い都市なので、慣れない運転はご自身でするのは避けましょう。
また、運転手に依頼する場合でも交通渋滞を考慮し時間には余裕を持ち、運転手に無理な運転をお願いしないようにしましょう。
2、自動車保険に加入する(旅行の場合も保険には加入しておきましょう!)
軽い物損事故の場合は、警察への通報義務はなく、基本的にその場で示談となるそうです。解決しない場合は、ともに車の運転手さんが警察に行くことになります。
3、事故現場の写真等は撮影しておく
事後にお互いの意見が食い違わないためにも、状況証拠としての写真を撮影しておく必要があります。相手の車、ナンバー、身分証明証等も念のために控えておきましょう。(双方に必要になります)
4、人身事故の場合は…
物損ではなく人身事故の場合は、相手の負傷者の状況を見た上で、自身の車やタクシーで負傷者を病院に連れていきましょう。臨機応変な対応が必要です。
ちなみに、救急車は23時間いつでも依頼できます。(救急車を呼ぶ場合は118)ですが、公共の救急車と言いつつも来ることがないので、直接病院に連絡を取る必要があります。
5、警察に行く場合は…
語学に堪能であれば大丈夫ですが、苦手な場合は通訳者を帯同しましょう。また、報告書等へのサインを求められた場合には内容を確認した上で、サインをするように。万が一、内容の相違がある場合、解決に至らない場合、またトラブルとなった場合は、日本領事館へ連絡を取ることも頭に入れておくこと。
事故に遭わないことが一番ですが、万が一のトラブルに巻き込まれた時には、落ち着いて対処を行いましょう。また、実際に大きな事故となった場合には人に囲まれたり、違うトラブルが生じる場合もあります。
今ではスマホがありますので、状況はきちんと写真に収めることであとからのトラブルを避けることが可能となります。
まとめ

本記事では、インドネシアの交通事情について詳しく解説しました。
日本では「安全運行と定時通り」が当たり前の感覚で、どこへ行くにも便利な公共交通機関に恵まれていますが、インドネシアでは同じようにいかないのが現状です。
車やバイクが多い分、実は人の優先順位が下げられているのが現状です。
旅行をするにしても、暮らすにしても、その不便さを感じることがあるはずです。
しかし、ここ数年でインドネシアの交通事情は大きく進化しています。
ビジネスの可能性を広げるためにも、重要なのはまず彼らがおかれている状況を知ること。
交通のインフラはその国の成長規模を知るきっかけとなります。これから先ますます発展していくインドネシアの状況からは目が離せません。
私たちは日本企業のインドネシアへの進出を10年に渡りサポートしています。
「インドネシアに進出しようか悩んでいる」という企業様は、ぜひ一度お気軽に弊社までご相談ください。